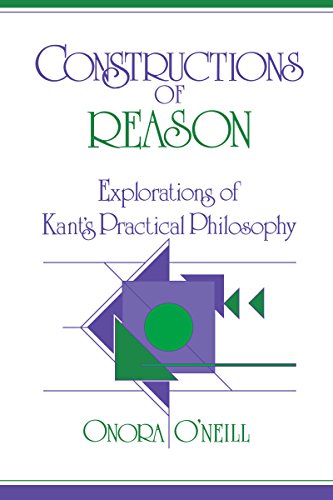教育(※1)やボランティア活動(※2)について倫理学的に考える際に、カントの「不完全義務」は有効な概念である。一般的に「不完全義務」は「例外を許す義務」であると解釈されることがある。しかしこの解釈は誤っていると考えられる。
この見解が正しいのであれば、その誤解の原因は『道徳形而上学の基礎づけ』(以下『基礎づけ』と略記)でのカント自身の記述にあるように思われる。
本稿では、カント道徳哲学の中から手がかりを探し出し「不完全義務」を解釈し直すことである。今回の結論は、次の通りである。
「不完全義務」は「例外を許す義務」ではなく、「活動の余地」を持つ「義務」である。
この結論に至るための道筋としての内容は、次の通りである。
[内容]
【第1回】『基礎づけ』での「不完全義務」の位置づけ
【第2回】「活動の余地」としての「不完全義務」
【第2回】まとめ
以上の作業はカント道徳哲学の発展に繋がるし、応用倫理学に関してもカントの議論の有効性を改めて示すことに繋がるだろう。
■『基礎づけ』での「不完全義務」の位置づけ
まず、『基礎づけ』での「不完全義務」の記述を確認する。カントは『基礎づけ』で「定言命法」の「普遍的法則の方式」(※3)を導出した後、「義務」を4つに分類する。すなわち、「われわれ自身に対する義務と他人に対する義務」(Ⅳ,421)及び「完全な義務と不完全な義務」(ibid.)である。その後、「義務」の事例をカントは4つ挙げる(※4)。
この箇所の脚注で「義務」の区分を『人倫の形而上学』に全面的に留保し、単に任意の形で示すに留めるとしながら、カントは次のように述べる。
私はここで完全な義務ということで、傾向性の利益のための例外を許さない義務を理解する。それゆえ私は、たんに外的な完全義務だけでなく、内的な完全義務をも認めるのであって、このことは学校で採用されている用語法に反している。しかし私はここで弁解しようとは思わない。(Ⅳ,421)
この引用箇所からも分かるように、「完全義務」をカントは「傾向性の利益のための例外を許さない義務」と定義する。一方、この箇所で「不完全義務」についてカントは何も語らない。
この箇所に即して考えるならば、「不完全義務」は「傾向性の利益のための例外を許す義務」となるだろう。ペイトンも自身の著作の中で、「不完全義務」を次のように解釈する。
カントによれば、完全義務は傾向に都合のよいような例外を認めたりはしない。とすると、不完全義務はそうした例外を許すということが示唆されているわけである。(Paton,1958,邦頁216)
【参考:Categorical Imperative】
このように『基礎づけ』でのカントの記述を受けて、ペイトンは「完全義務」に対して「不完全義務」を「例外を許す義務」であると理解する。また、ベックは「不完全義務」を「格率」同士の衝突が生じた場合、例外が許されてもよい「義務」であると解釈する。以下、ベックの記述を引用する。
完全義務とは、直接的に命ぜられ得るか又はその格率がある行為を要求する行為の事である。というのは矛盾する格率は、それが法則に適った時、自己矛盾だからである。不完全義務は、一つの規則への服従が他と相克することを避ける為に、例外の規則が適用されてもよい義務である。道徳的義務は不完全義務で、法的義務は完全義務である。(Beck,1960,邦頁191)
【参考:A Commentary on Kant's Critique of Practical Reason】
ベックの解釈では、ある「格率」が「道徳法則」に適った時、自己矛盾に陥るので「完全義務」は「ある行為を要求する行為」である。
一方、ひとつの「道徳的規則」つまり「格率」への服従が他と相克することを避けるため、「不完全義務」に「例外の規則」をベックは認める。
以上2つの記述からも分かるように、両者共に「不完全義務」を「例外を許す義務」として位置づけている。この図式からすると、「完全義務」は一切の例外を許さない「義務」である一方、「不完全義務」は例外を認めてもいいことになるだろう。
確かに一般的には、規則や原則には必ず例外があることも認めなければならないだろう。しかし例外を認めてしまうと、カント道徳哲学の体系から大きく外れてしまう。なぜなら、『基礎づけ』での目的は「道徳性の最上の原理を探求し、それを確定すること」(Ⅳ,392)だからである。
また別の見方をすれば、道徳の「普遍化可能性」を維持する目線をカントは常に保ち続けているとも考えられる。カント道徳哲学で、この態度は一貫していると考えてもよい。したがって「義務」に例外を認める立場は、カント道徳哲学にとってあり得ないと考えざるを得ない。
ではどのように「不完全義務」を解釈すればよいか。その手がかりとなるのは、次の2点である。
1つ目は『基礎づけ』で「不完全義務」を「より広い義務」(Ⅳ,424)とカントが述べている点である。「義務」の事例を4つ挙げた後、カントは「完全義務」を「より狭い義務」(ibid.)と呼び、「不完全義務」を「より広い義務」と言い換えている。
2つ目は『人倫の形而上学』の中で「法論」として「完全義務」を、「徳論」として「不完全義務」について論じている点である。カントは「義務」の区分を『人倫の形而上学』に委ねているが、本書の中で「法論」として「完全義務」を「徳論」として「不完全義務」について詳細に記述している。
ベックが指摘した通り、法的義務は「完全義務」であり道徳的義務が「不完全義務」と考えてよい。そして『人倫の形而上学』の中で『基礎づけ』で登場する「より広い義務」が、「活動の余地」として再定義されている。
【参考:人倫の形而上学】
では、『人倫の形而上学』では具体的にどう「不完全義務」が位置づけられているか。【第2回】では、『人倫の形而上学』をテキストに「不完全義務」について追究する。【続く】
【次の記事】
(※1)例えば、O’Neil,O,1989:Constructions of Reason:Explorations of Kant’s Practical Philosophy 第10章 参照.
【参考:Construction of Reason】
【参考:理性の構成】
(※2)例えば、過去記事を参照.【参考:過去記事】
(※3)「汝の意志の格率が普遍的法則法則となることを、その格率を通じて汝が同時に意欲することができるような、そうした格率に従ってのみ行為せよ」(Ⅳ,421)という「定言命法」を指す。「普遍的法則の方式」はPatonが付けた「定言命法」の区分のひとつである。(Paton,1958,邦頁190-213 参照.)
(※4) 4つの「義務」の事例とは、すなわち自殺・虚言・怠惰・不親切である。(Ⅳ,421-424 参照.)
※以下の過去記事も参照
※今回参照したペイトンの邦訳書[杉田聡訳]は絶版。以下の紀要論文が参考になるだろう。
高野 ・野々村,1981:翻訳 H.J.ペイトン著「定言的命法」(1)、『大阪府立工業高等専門学校研究紀要 15』所収、大阪府立工業高等専門学校、1981年. http://doi.org/10.24729/00008055
※今回参照したベックの邦訳書。
![道徳形而上学の基礎づけ [新装版] 道徳形而上学の基礎づけ [新装版]](https://m.media-amazon.com/images/I/410MXW7652L._SL500_.jpg)